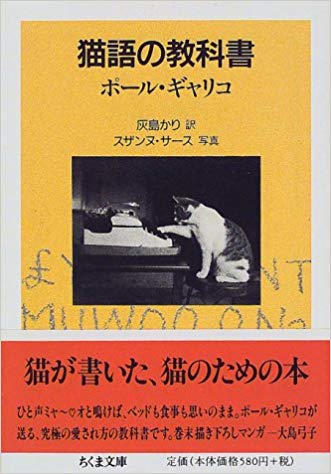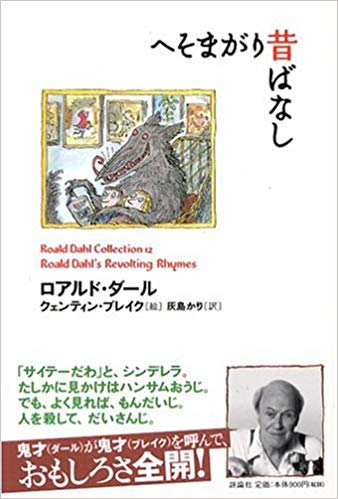PERSONS
子どもたちが必要としてくれる本を作りたい。
児童文学の魅力を美しく楽しい日本語で伝える
ビジュアルと文章の関係を教わった雑誌編集者時代
高校生の頃にイギリスのファンタジー作品を読むのが大好きになり、いつか子どもの本に関わる仕事がしたいと思っていました。『指輪物語』の作者として有名なトールキンという作家がいますが、その系統で日本ではまだあまり知られていなかったアラン・ガーナーというファンタジー作家が私は大好きで、人文学部英文科を専攻した大学の卒業論文ではガーナーについて書きました。
そしてちょうど卒業間際に、資生堂が出している『花椿』という、私の大好きなPR誌の編集部が人をさがしているという話がまわってきて、そこで働くことにしました。編集部では雑誌にもっと海外のテイストを取り入れていきたいと考えていて、英語ができる人材をさがしていたのです。原稿依頼や写真撮影などのふつうの編集の仕事の他に、海外の雑誌を読んで、これぞと思う記事や視点など、何でもいいから見つけてきなさいと言われて、雑誌見放題。忙しかったけれど、とても楽しい仕事でした。
子どもの本の仕事をしたいという思いはずっと持ち続けていたので、PR誌の編集の仕事はちょっと遠回りではあったのですが、今思えば、あの時代も今の仕事にとって決して無駄ではなかったんです。優秀なアートディレクターから、ビジュアルと文章の関係を徹底して叩きこまれたのが『花椿』の時代でした。それは今、絵本の仕事をするにあたって非常に役立っています。その時は遠回りに思えても、実は後で役立つことって多いんじゃないでしょうか。人間のすることって、そんなに無駄はないんだなと思います。
子どもの本の仕事をする前に、実は翻訳の仕事をするチャンスが巡ってきたんです。翻訳を勉強していた時期があって、その先生からの紹介でした。決して私が出来の良い生徒だったわけではなく、むしろその逆で、オーソドックスに訳すだけでは不満で、いつもちょっと変わった文体にしたがる生徒だったのですが、それが功を奏したようです。
ポール・ギャリコという作家の『猫語の教科書』という作品なのですが、出版までには紆余曲折がありました。最初に版権を持っていた出版社は、若い人が読みやすい本にしたい、ついては現代の女の子っぽい文体にしてはどうか、という意向でした。そこで、広告のコピーや雑誌記事を書いていた私なら読みやすい文章を書けるのではないか、また翻訳を学んでいる生徒の中でも、いつも珍妙な文体で訳してくるから、女の子っぽいキャピキャピした文体もできるだろう、ということで私に白羽の矢が立ったのです。 でも、原書を読んでみたら、内容はちっともキャピキャピしていないんです。著者のポール・キャリコは、非常に透徹した目で人間を観察することに優れた作家で、どのように訳せばいいのか本当に困ってしまって……。でも編集部の意向ですから、それにできるかぎり沿うように、口語的な口調で訳しはじめました。そしたら、その出版社が全面的に出版業から撤退することになり、版権を手放してしまったんです。努力して半分くらい訳していたのに日の目を見ないことになり、「あぁ、こういうこともあるんだ」と落胆しました。
でもその後、ありがたいことに版権を引き継ぐ出版社がすぐに現れたんです。筑摩書房でした。さっそく編集者の方にお会いして、私の翻訳文を見ていただいたのですが、「何なんですか、この訳文は」と編集者の方が愕然とされてしまって。筑摩書房は文学色の強い出版社ですし、ポール・ギャリコという作家も文学路線です。もっとオーソドックスな訳を、ということで、全面的に赤が入りました。でも、ゴミ箱行きだったものが生き残ったのです。今度こそ絶対に出版したいと思い、言われたように必死にオーソドックスな訳に書き替えました。
そしたら、今度はその編集者が会社をお辞めになって、次に担当になった編集者は、そのオーソドックスな訳を読んで「生き生きしたところがないし、面白くない」と言うのです。直せと言われて直した私は心外で、前のキャピキャピした訳も見せて事の経緯を説明しました。すると、その方は「前の訳のほうが断然面白い」と。ただ、そこまでキャピキャピさせずに、今のように“普通すぎて面白くない訳”でもなく、その中間のほどよいところで口語的に訳してくださいと言われて、また書き直しです。ものすごく時間がかかったのですが、ちょうど良いところを探りながら口語調で訳したところ「大変良い」と言っていただいて。結果的に納得のいく訳で出版できましたし、うれしいことにベストセラーとなりました。
私は最初の訳書でこのような経験をして、おかげでそれ以降、あまり怖いものがなくなりました。オーソドックスな訳も、とってもずっこけた訳も、何でもできるという自信になり、幅広い仕事ができるようになりました。
イギリスで児童文学を学んだ1年半は忘れられない貴重な体験
『猫語の教科書』を訳している途中、夫の仕事の都合で2年ほどイギリスで暮らすことになり、これは大好きなイギリスの児童文学を学べるチャンスだ! とばかりに、必死で大学の児童文学のコースを探しました。見つけたのはサリー大学ローハンプトン大学院という、当時設立2年目の新しい大学院でした。私は昔から授業を大人しく聞くことが苦手な生徒でしたが、ここでのやり方は、講師が指定した本を読んできて、それについてディスカッションするという実に自由なものでした。
ただ、当時の私の英語力では、イギリス人の生徒と同じというわけにはいきません。「来週までにこの7冊を読んできてください」と言われても、1冊の途中まで読むのが精一杯。ほかは目次だけ眺めていくとか、ひどいときは1ページもめくっていないとか。でも、このときに実感しました。海外では英語はなめらかにしゃべれることが大事なのではなくて、自分の意見を持つことが大事だ、とよく言われますが、それはまったく本当なんですね。予習が十分でないとはいえ、児童文学について熱い思いを持っていましたので、発言したいことはいろいろとあります。例えば「日本ではこのファンタジーはこんなふうに受け取られている。イギリスとは違うでしょう。でも、こういう考え方もあるって、面白いでしょう」といったことを、つたない英語で一生懸命発言すると、みな耳を傾けてくれるんです。聞いてもらえるとうれしいから、次はもっと言いたいことを持って行こうと頑張る。その積み重ねで、何とか授業にしがみつくように付いていきました。ああ、学ぶというのはこういうことなんだな、と実感しました。
イギリスで面白い絵本や児童書をいっぱい読みましたので、それを翻訳したいという思いがありましたが、『猫語の教科書』という訳書があったとはいえ、これは児童書ではなかったので、売り込み先の出版社にあてはありません。そこで、昔からいちばん好きで、アラン・ガーナーの本を出していた評論社という出版社の編集部に宛てて手紙を書いたんです。評論社から出版されているアラン・ガーナーの作品について、ちょっと辛口の意見も含めて自分の考えを綴り、最後に「ご紹介したい原書があります。お目に掛かる機会をいただけないでしょうか?」と結びました。そしたら編集長からお返事をいただき、会っていただけることになりました。編集長から後で聞いたのですが、「こういう手紙はたくさんもらいますが、声を掛けたのはあなたが初めてでした」ということでした。おそらく、私のアラン・ガーナーへの思いが通じたのだと思います。
評論社に私が持ち込んだ本は、結局、版権の問題で出版は叶わなかったのですが、ほかの本を「翻訳してみませんか」と渡されました。『お助けナブラーが、やってくる』という本です。私はそれでもう依頼されたつもりだったのですが、「一章分訳して持ってきてください」と言われ、実はそれはトライアルだったようです。私なりに工夫して訳して持って行ったところOKが出て、無事1冊訳せることになりました。
読者である子どもが喜ぶ本、子どもの役に立つ本を作っていきたい。
『お助けナブラーが、やってくる』は小学校低学年向けの読み物です。両親がケンカばかりで主人公の男の子は、いつも泣いているのですが、あるときナブラーというヘンな奴がやってくるんです。それは現実を逃避したい男の子が作り上げた空想の友だちなんですが、ナブラーの助けを借りて、両親が離婚をするという辛い状況も乗り越えて、前向きに生きていくというお話です。
この作品はちょっとハウツーのようなところがあるので、児童文学界で評価されるタイプのものではないのですが、私はとっても好きなんです。同じような境遇の子どもが読んだら、どんなに助かるだろうって。随分前から児童養護施設で絵本の読み聞かせをしていて、そこでも感じるのですが、子どもにとって本って「役に立つもの」なんですよね。本を読むことで、子どもが慰められたり、力づけられたり、それが児童書の本当の役目なんだ。児童文学の研究者が好む作品よりも、読者である子どもたちを喜ばせる作品を作っていきたい。以来、私はずっとそういう思いで翻訳を続けています。
私が訳した中で、最も文学性が高く、児童文学界の方に評価される本というと、ローズマリー・サトクリフの『ケルトの白馬』だと思います。サトクリフはイギリスの児童文学者のあいだでも、最も尊敬されている作家の一人で、素晴らしい英語の書き手ということでも定評があります。障害があって車椅子での不自由な生活なのですが、心は誰よりも自由な、そんな作家なんです。イギリスにいるときに読んで、すごく面白いと思ったのですが、日本では猪熊葉子先生という大御所の翻訳家の方が訳されているので、自分が訳す機会はないだろうと思っていました。ところが、ほるぷ出版に絵本の売り込みにいったところ、持って行った本は全部却下されたのですが、この『ケルトの白馬』を「出版する予定があるのですが、興味はありませんか?」と。興味があるどころの騒ぎではありません。「絶対にやらせてください」と言って、二度と手放すまいという気持ちで原書を預かって帰ってきました。
そんな経緯で訳すことになった本なのですが、サトクリフの言葉を一字一句大切に、原文の美しさを損なわないようにできるかぎり美しい日本語で、しかも読みやすく訳そうと、本当に苦労して訳しました。
私の訳書の中で、それと対極にあるのがロアルド・ダールの作品です。『チョコレート工場の秘密』が映画化されたのでご存じの方も多いと思いますが、J・K・ローリングが出てくるまで、イギリスの子どもたちにダントツ1位の人気を誇っていたのがロアルド・ダールです。イギリスにはマンガがないので、その代わりをするような本で、それゆえにお母さん方からは「そんなものばかり読んで……」と言われてしまうような作家です。何作品か訳したのですが、なかでも『へそまがり昔話』は韻文で書かれたとっても可笑しいパロディで、ひっくり返ってワッハッハと読める本です。例えば『白雪姫』は、“7人の小びと”ならぬ“7人の騎手”が出てきて、継母のところから盗んできた魔法の鏡から競馬の勝ち馬を聞き出して、大穴当てて億万長者になるというぐあい。その馬の名前が、英国民なら誰でも知っている、日本だったら“ハイセイコー”のような有名な馬の名前をもじったものだったのですが、それをそのままカタカナにても面白さは伝わらないので、私は借金まみれの7人の騎手にちなんで“シャッキンホマレ”という名前にしました。ダールは子どもたちが大笑いする姿を期待して書いているわけですから、それを翻訳する場合は、日本語で読んだ日本の子どもたちが同じように大笑いしなければ意味がありません。サトクリフを正確に美しく訳そうとしたのとは反対に、ダールのほうはとにかく楽しく読み進めてもらえるように、ありとあらゆる工夫をこらしました。
サトクリフも、ダールも、どちらの翻訳も難しくて、取りかかっているときは苦しかったです。苦しいことの連続なのですが、でもどちらも楽しかった。苦しみと楽しさは隣り合わせですね。
自分の中にある日本語を、豊かに
翻訳者には、やはり何といっても本を読むのが好きな人が向いていると思います。本を読むのが好きだと、なかでもとりわけ好きな本というのが出てきて、そうするとその本は一度だけではなく何度も読み返すことになることでしょう。翻訳するということは、読み込むことです。一字一句、すべて読み込んでいくわけですから、好きになった本を何度も読み込んでいくうちに、その本のことをどんどん好きになっていったとしたら、それは翻訳のプロになる芽が出てきたということではないでしょうか。
それから、翻訳をするためには、自分の中にある日本語が豊かでなければなりません。日本語を豊かにしてくれるものは何だろうと考えたのですが、古典だという気がしています。私は坂東玉三郎の大ファンで、玉三郎が歌舞伎座に出ているときは忙しいのですが(笑)、歌舞伎の言葉というのはわりあいと身体の中に入っていて、ときに訳文に出てきたりします。それから講談も好きで聞くのですが、あれは昔、文字を読めない市井の人々のために、浪人が辻に立って太平記などの軍事物を読んで聞かせたのが始まりだそうです。あれこそ元祖読み聞かせなんですね。講談は“語る”とは言わずに“読む”と言うそうです。この講談の口調がとてもリズミカルで、絵本の翻訳にぴったり合うことがあります。落語にしても、浄瑠璃にしても、伝統芸能というのは豊かな日本語の宝庫だと思います。あまり馴染みがないという方は、一度体験してみるとよいのではないでしょうか。
取材協力
灰島かりさん
国際基督教大学卒業。化粧品会社が発行するPR誌の編集を経て、フリーに。家族の転勤でイギリスに移り住んだ際に、サリー大学ローハンプトン大学院に入学し、約1年半のあいだ児童文学を学ぶ。帰国後、出版社への企画持ち込みなどを積極的に行い、翻訳の仕事につなげる。現在は、絵本や児童文学の翻訳者・研究者、白百合女子大他講師として活躍。訳書に『ケルトの白馬』『へそまがり昔話』『負けないパティシエガール』『びくびくビリー』等、著書に『あいうえおのえほん』『ラブレターを書こう』『絵本翻訳教室へようこそ』『絵本をひらく』等がある。