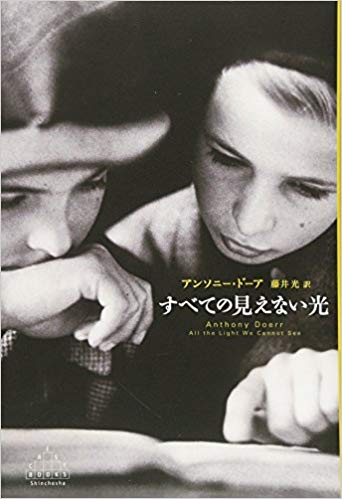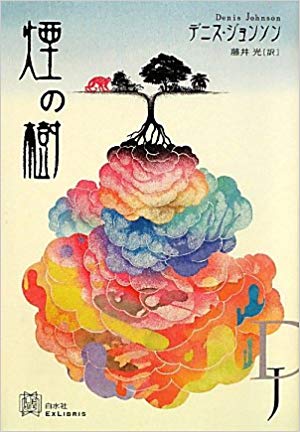PERSONS
「フェイク」が溢れる時代だからこそ考えたい
作家が作る、フィクションの意義
同志社大学の准教授でもある藤井さんが翻訳の仕事を始めるきっかけとなったのは、柴田元幸氏の『モンキービジネス』だったそうです。
「自分とは誰か」から「他者への共感」へ
グローバル化するアメリカ文学
アメリカ文学のごく最近のブームは、「ディストピア」と呼ばれる、破滅した、もしくはしかけている世界を舞台とする小説がたくさん出ているという現象があります。トランプ現象の産物とも言えるでしょうか。そこに性や人種といった主題が取り込まれているのが、目下のところ目立つ作風です。
ジャンルや作風はかなり多様になっていて、今の流行りは~イズム、ということはちょっと言いづらいんですが、確実にあるのは、「他者への共感」という問題を探求する作家・作品が多いことです。アメリカ文学だと、「自分とは誰か」という問いが大きなテーマなんですが、最近は「自分は誰に共感できるか」というテーマがある小説が多いかなと感じています。アンソニー・ドーアはアメリカ人が出てこない小説『すべての見えない光』を書いて、そこでドイツ人の少年とフランス人の少女が一瞬心を通わせる物語を作りました。いい意味でのグローバル化が文学にもたらしたテーマだろうと思います。
僕は非英語圏出身の作家が英語で書いた作品を訳すこともありますが、英語ネイティブによる作品と比較すると、訳しやすさと訳しづらさ、どちらもありますね。訳しやすいと思える理由は、そうした作家たちが「ものすごく英語らしい英語」を使っていないという点です。英語ネイティブが書く英語らしい英語は、日本語に翻訳するとなると、かなり語順をいじらないと難しいことが多いんですね。逆に、非英語圏出身の作家たちの書く英語は、語彙や構文が目に見えてシンプルなものでなくても、語順をあまりいじらなくても日本語に翻訳することができるケースが多いです。英語以外の外国語がベースにあるせいなのかどうか、僕にはちょっと判断できませんが。英語から「微妙に空気が抜けている」感じでしょうか。
訳しづらいのは、そうやって英語が「微妙に抜けている」感じをどう再現できるのかという点で……。日本語としてあまりに自然になっていたら、原文の面白さが半減しているということだし、でも英語でやっていることをそのまま日本語ではできないし……。おそらく正解があるわけでもないので、小説ごとに、ああでもないこうでもない、と試行錯誤する毎日です。
日頃の僕は、自分が読みたい小説を読んでいますが、当然ながらその時点で、作品選びはかなり偏ってきます。最近は、移民や難民の小説をよく読むのですが、同時に不思議な異界感のある小説が僕は好きなので、両方の要素が入っているとなると、かなり変な小説になります。基本的には、真面目なのかひねくれているのか半々のような作品が好みです。インド出身でニューヨーク在住のカニシュク・サルーア(Kanishk Tharoor)の短編集Swimmer Among the Starsなんか、「移住」とか「ホームの喪失」を主題にして、でもそれをモロッコに贈られたインドゾウの旅路とかアレクサンドロス大王の中国遠征(もちろん創作です)に託すという作風で、かなりツボでした。
そうしたものを読みながら、ちょくちょく編集者の方ともやりとりがあるので、その中で企画にまとまっていく作品が出てくる、というのが僕の日常です。作品のレジュメをまとめるときは、物語としての面白さを伝えるだけでなく、この時代においてその物語がどんな意味を持っているのか、という点も意識するようにしています。今はフェイクニュースなどの「嘘」が溢れる時代でもありますから、作家が作るフィクションの意義というのは、しっかりと考えておくべき問題かなと思います。
柴田元幸氏との出会い
高校生のときから、英語は結構好きな科目でした。小さなころからジグソーパズルがすごく好きだったんですが、たぶん、ジグソーパズルと英語への興味はつながっているんだと思います。最初はばらばらのピースが、じーっと見ているとつながりが分かってきて、だんだん絵柄ができ上がっていくジグソーパズルって、外国語の文章の意味がだんだん分かってくるのと似ているじゃないですか。それに加えて、ある程度の長文だと、自分があまり知らない内容が書かれていることもよくあって、「何が書いてあるんだろう」という純粋な好奇心もくすぐられます。なので、英語の長文を読むのはわりと好きでした。そうは言っても、当時の僕には洋書を1冊読むなんて想像もできませんでしたが。
大学に入ってまず専攻しようと思ったのは、実は文学ではなく歴史(西洋史)の分野でした。その頃は、文学を勉強するってどういうことなのか、いまいちイメージをつかめていなかったせいでもあります。ところが、大学2年生のときに歴史の講座に入ってみて勉強を始めたら、どうも想像と違いました。何が違うんだろう、としばらくモヤモヤしていたんですが、そのうちに、自分が求めているのは「ストーリー性」なんだろうと気がつきました。
ちょうどそのときに、アメリカ映画の授業でレポートを何度も書いているうちに、物語について考えることの面白さがわかってきたこともあって、3年生からアメリカ文学に移りました。英語文学を選んだのにイギリス文学ではなかったのは、アメリカ文化に触れることがわりと多かったせいもありますし、映画や音楽ではかなり明るいイメージを発信しているのに、文学は暗いものが多いというギャップが気になったせいでもあります。基本的に僕は暗いものが好みなので。
大学4年生のときに、授業のテキストとは関係なく自分で洋書を初めて買いました。アンナ・カヴァンの『氷』の原書です。核戦争の余波で世界が氷に閉ざされていくという設定だったので、大学のあった冬の北海道で読むとあまりに身につまされて、忘れられない読書経験でした。その勢いで、ちょっと日本語に翻訳してみようかと思い立って挑戦してみたんですが、確か3段落目くらいで、どうにも日本語が出てこない文にぶち当たって見事に挫折しました。当時は英語力も日本語力も純粋に足りなかったんだと思います。
そのあと、大学院生になって、ポール・オースターから入って現代アメリカ文学を勉強していったんですが、そうすると柴田元幸先生の翻訳に触れる機会が非常に多いですし、日本語にまだ訳されていない作家や小説を扱うことも増えていきますから、必然的に翻訳そのものへの憧れは芽生えました。でも実力不足を一度思い知ったので、まあ余興ぐらいにしておこうと思っていました(笑)。
大学院で未訳の短編について発表するときに、ちょっと日本語訳を作ってみて大学院生の仲間の人たちに読んでもらう、ということはやりました。あと、僕は大学院生最後の年に結婚したんですが、日本・アジア古代史の研究者である妻も本が好きだし、式のゲストの人たちも文学部の先生と同級生が多いし、ということで、本を作ってみんなに贈ろうかという話になったんです。2人で英語の掌編をいくつか選んで日本語に翻訳して、大学生協で製本してもらって結婚式の引き出物を作りました。しばらくしてから読み返すと、ある作品で一人称の語り手が最初は「俺」だったのが途中から「僕」に変わっていたり、色々と誤訳の多い引き出物でしたが(笑)。それでも、とりあえず翻訳が形になる面白さは味わえたので、後から見ればそれが僕の翻訳者としての原点なのかもしれません。
本格的に翻訳を始めたのは2007年からですね。大学院のときにオースターの詩について書いた論文を柴田元幸先生に読んでいただき、現代アメリカ作家について研究すると決めてからは、先生には博士論文の副査にもなっていただきました。博士課程を終えて、研究員として東京大学に受け入れてもらったのが2007年で、ちょうど柴田先生が『モンキービジネス』を立ち上げるタイミングだったので、1つエッセイを翻訳してみないか、と声をかけていただきました。
そのときに、初めて翻訳の原稿にコメントや添削を入れていただいて、わりあい直訳でもいいところ、ちょっと原文から離れて日本語らしい表現を考えるべきところをどう区別するのか、という点ですごく勉強になりました。野球のエッセイで、投手が打者をあっさり打ち取ってダグアウトに帰っていく、という場面で、”as if”構文が使われていて、僕はそこを「打者たちを翻弄するのは当たり前だと言わんばかりに」ダグアウトへと歩いていく、と訳したんですが、柴田先生の案は「相手チームをいともたやすく抑え込んだ」投手が「涼しい顔で」マウンドからすたすた降りていく、というものでした。自分の訳との違いを見て、そうか翻訳ってこういうものなんだ、とどこか腑に落ちたのが、僕にとっては大きな経験だったと思います。
もうひとつ、僕の翻訳者としての悪癖もそのときに露呈しました。エッセイでも物語でも、クライマックスの場面を翻訳するときに、原文を3~4行飛ばしてしまうという癖です。訳者の僕が勝手に盛り上がってしまって、早く次の文章を訳したいと思うせいで、いい文章なのにひょっこり抜けてしまう……。その後も2、3回やらかしているので、もはや不治の病なのかもしれません(笑)。
実は、僕は講座で学ぶということができない性分なんです。先生に付いてレッスンを受ける、というのがどうしても性に合わないというか。何事も、とにかく自分で試行錯誤しながらどうにかやってみよう、という性格です。ということもあって、免許とか資格を得るということにも、どうにもなじめなくて、運転免許も教員免許も、何の資格も持っていません。そんな人間が教師をしているのは詐欺というか、控えめに言っても無理があると思いますが……。
そのようなわけで、柴田先生の研究室でも翻訳の授業には参加せずじまいでした。長編・短編小説を読んできて話し合うという授業には参加していて、そのときに、自分にとって小説が「合う・合わない」という相性を見つめ直す機会を、柴田先生や、一緒に授業を受けていた人たちとのやり取りから与えてもらったと思います。小説でも詩的な表現とかイメージに支えられている文章が僕は好きで、それを音楽的だと感じるんですが、詩的表現を突き詰めると、物語性はなくてもいいと思い込んでしまう危険もあるんですね。断章を連ねて1冊の本になっていて、プロットはない小説とか。僕の興味がそこに行きかけていたときに、柴田先生や周りの人たちと話をしても、少し盛り上がらなかったことがあって、そうか物語として面白いかどうかもちゃんと考えたほうがいいんだな、と読書の軌道修正をした記憶があります。
だから『モンキービジネス』のエッセイ翻訳は、もう実地訓練という状態でしたね。とりあえず訳を自分なりに作ってみて、それを推敲するなかで、ちょっとしたヒントがあればという思いで、いくつか翻訳についての本を手にとってみました。といっても、僕はノウハウ本が苦手なのであまり読まず、『翻訳夜話』(村上春樹・柴田元幸著)が一番参考になった記憶があります。そのなかで、村上さんが「不正確でもいいから翻訳は早く出してあげるほうがいい」という趣旨のことをおっしゃっていて、その文章を読んだときに、これを心の支えにしていこう、と心底感謝しました(笑)。あとは、文章のリズムが大事という話も記憶に残っています。小説を翻訳するときには、どういうリズム感が合っているか自分なりに考えるようになりました。
作品完成まで18カ月
はじめての訳書『煙の樹』
最初の訳書はデニス・ジョンソンの『煙の樹』です。原書で614ページ、翻訳で658ページという数字は、今でも暗記しています。
そもそも、僕はデニス・ジョンソンの小説がすごく好きで、大学院生のときにほとんど全部読んでいたし、博士論文でも彼の小説をひとつ取り上げていたんです。そのあと2007年に東京に来たら、ちょうど白水社が〈エクス・リブリス〉という海外小説のシリーズを立ち上げるところで、ジョンソンの『ジーザス・サン』が柴田先生の訳で出ることになっていました。その年にジョンソンの新作として大作『煙の樹』がアメリカで刊行されて、全米図書賞も獲ったので、白水社がそれも検討することになったときに、柴田先生から訳者候補として紹介していただいたという流れで、翻訳することになりました。といっても、そのときの僕はそうしたことをあまり知らなくて、気がついたら企画が通って1冊翻訳することになっていました(笑)。
完成するまで18ヶ月かかりました。一番難しかったのは推敲の作業です。まず第1稿を作ろうとして、英語を日本語にしていって本の最後までたどり着くのに半年くらいかかったと思いますが、その先に何をすればいいのか、いまひとつ分からない。今であれば、まずは紙に書いた原稿をパソコンに打ち込んで、印刷して原文と照らし合わせてチェックして、という個人的な手順がもう決まっているんですが、当時はそれもなかったので、パソコンに打ち込んではみたものの、次は何をやればいいんだっけ、とか、同じような見直しを2回もやってしまうとか、とにかく暗中模索のプロセスでした。
あと、長い小説になると、会話文がたくさんあるとありがたいんですね。場の雰囲気とか、登場人物のキャラクターとかをつかめていたら、会話はノリでかなり楽に訳せます。逆に、地の文でページの隅から隅までぎっちり文字が詰まっているのを見ると、ちょっと気持ちがしんどい。それでもとにかく進んでいくことが大事なのだと学びました。
藤井流 翻訳手順
今のところ、翻訳は第4稿まで作って完成させる、というのが僕の基本的な流れです。
—-
①第1稿は、原文を日本語に直していく作業です。B4サイズの裏紙(要するに、過去の翻訳の初校・再校ゲラの紙)に、原文を見て思いついた日本語を書きなぐっていって、とにかく1冊の本を最後まで進めます。
②裏紙に書いた日本語を、できれば2週間くらいでパソコンに打ち込んでいきます。打ち込みながら、全体の語りのトーンとか訳語の選択などを修正していきます。たいてい、第1稿の最初のほうはいまいち語り口もつかめていなくて、最後のほうになると作品の持つ質感に僕のほうが合わせられているので、最後あたりのトーンを優先して、原稿の前半をチューニングし直すような感じでしょうか。
③打ち込んだ原稿をプリントアウトして、原文と照らし合わせます。誤訳がないか、あるいは原文からずれた訳になっていないか、そして、大事な場面で訳し忘れた「抜け」がないかをチェックしていきます。これ、あるんですよ。不治の病なんで(笑)。この②と③が第2稿です。
④あとは日本語のみを推敲します。第3稿では、英語に引っ張られすぎていて日本語として不自然な箇所を中心に修正します。かといって、あまりに日本語の自然さを追求しても原文の色合いが消えてしまうので、やりすぎないように気をつけています。
⑤第4稿は、文の長さを調整したりして、「文章のリズム」を整えることが基本的な作業です。できれば一日のうちに最初から最後まで読み通して、全体のリズム感が同じものになるようにします。これは長編でも短編集でも同じです。
⑥完成したら疲れ果てて、熱を出します(笑)。回復して頭がすっきりしたら、次の作品に取り掛かります。
—-
音の響きや風の感触を、登場人物と共有する
基本的には、小説の舞台となる土地が実在したとしても、翻訳者は必ずしも訪れる必要はないと僕は思います。大事なことは小説そのものにすべて書いてあるので。でも、訳していると土地にも思い入れが生じるので、やっぱり行ってみたくなるんですね。『すべての見えない光』のように、海の音とか、街路の風景が細やかに描かれていると、自分でもそれを感じてみたいなという気になってきます。
また、『すべての見えない光』には、盲目の少女マリー=ロールが、建物を触りながら通りを歩いていく場面がたくさん出てきます。彼女が歩数や手に当たる排水管を数えながら歩いているサン・マロの通りは、実際にはどんなところか、自分で歩いてみようと思って、小説にしたがって動いてみました。サン・マロは小さな町です。石畳を歩いていくときの音の響きとか、城壁を抜けた先にある浜辺と海の音や風の感触なんかを、フィクションの登場人物と共有するというのは、とても不思議で忘れがたい感覚です。そんなこともあって、マリー=ロールが初めてサン・マロの海辺に出るところ(P.234~P.235)は、個人的に一番心に残っている場面でもありますね。
翻訳していて、初めて作品の舞台になる土地を訪れたのは、ロレンス・ダレルの『アヴィニョン五重奏(全5巻)』を翻訳しているときでした。アヴィニョンという町とその近郊の持つ空気感がすごく強調されていたので、5冊翻訳するならちょっと体感しておこう、と思ったのがきっかけです。訪れる前に自分が作っていた訳の原稿と、実際の町の印象はそれほど変わらなかったので、やはり大事なのは作品そのものなのだと実感したんですが、それと同時に、作品内のA地点からB地点までの距離感とか、市街のサイズ感などは、行って確かめてみると、より翻訳のときに人の動きが明確にイメージできることにも気がつきました。あと、ダレルが書いているとおり、アヴィニョンには美味しい料理が多かったので、二重に得をした気分でした(笑)。
翻訳が好きだという偏愛を持ち続け、
育むことが大事
辞書は、標準的なコンテンツの電子辞書しか持っていないのですが、まあそれで致命的な誤訳や語彙不足に苦しむこともなかったので大丈夫かな、という感じでしょうか。出版社はどこでも良いので英和大辞典と、語彙が豊富な『リーダーズ・プラス』が入っていれば、単語の意味はほぼカバーできますし、あとは活用辞典があれば、言い回しが標準的なものか作品独自のものかは、ある程度まで判断できます。
あと、翻訳者の西崎憲さんが『文芸翻訳入門』で書いておられますが、文芸翻訳を目指すのであれば、参考書よりも日本の現代作家による小説を読むほうが、日本語力の向上に役立つと思います。たとえば、僕は松田青子さんの小説を家族相手に読み上げるのが好きなんですが、語り口調を少し硬くしたり軟らかくしたりといった語感の作り方を学ばせてもらっていると思います。
結局のところ、大事なのは翻訳が好きだという偏愛を持ち続けて育んでいくことだと思うので、翻訳家が書いたエッセイとか、翻訳について語る場とか、とにかく翻訳について語る言葉に触れる機会を持てれば、モチベーションの維持になるんじゃないでしょうか。翻訳好きにはいい人が多いというのが僕の持論なので、心の健康に役立つという利点もあるかもしませんし(笑)。
2017年の夏休みに、僕の勤めている大学のオープンキャンパスがあって、僕は学科紹介のブースに座っていました。英文学科ではこういう勉強ができて、留学制度はこうなっていて……という説明をする係だったので。すると、「自分で翻訳した本がある」という高校生がそこに現れて、その本を出すためにどうすればいいのかという相談が始まりました。思い入れのある本を自分で翻訳して出したくて、原稿はもうある、という話で、とりあえずその場では、第1章の翻訳に僕からちょこちょことアドバイスをさせてもらって、電子書籍の出版社もあるから、という話をしました。
その後、その高校生は電子書籍の出版社に実際に売り込みに行ったそうで、共訳者をつけたうえでクラウドファンディングの企画にする、というところまで話が進んでいるそうです。それが順調に行けば、実際に出版されることになります。
僕にとっても前代未聞の話だったんですが、ちょっとやそっとのことでは諦めずに自分から動くというのも大事なのだな、とそのとき分かりました。小規模でもこだわりをもった取り組みをしている出版社はたくさんあるので、自分にとって特別な本を翻訳出版したい、と思ったときには、あちこち訪ね歩いてみるのもいいのかもしれません。
あと、新刊の情報や反響は、インターネット上やSNSでわりとすぐに情報が手に入ります。でも、日本の出版社がそれをすべて追うことはできないし、読者もすべて読むことはできないので、翻訳者が「癖のあるフィルター」のように機能することも大事かなと思います。奇妙な世界のなかにリアルな感情がある作品が読みたいなら岸本佐知子さんについていけばいい、とか。そういう「癖」は、個人の偏った好みをとことん追求して出てくるものだと思うので、ブームとか話題とかに惑わされずに自分の好みを追いかける嗅覚があれば、他の人の入り込めない自分の場所を作れるんじゃないかと思います。
同時に、文芸翻訳はかかる時間や労力に比べて、それほどお金が戻ってくる世界ではないので、「コスパ」ってなにそれ? というくらいのメンタリティーがあるほうが翻訳に集中できると思います。
翻訳者に求められる数あるスキルのなかで、僕が最重要かつ最難関だと思っているのは、「締め切りを守る」能力なんです。文芸翻訳の場合だと、締め切りが延びることにはわりあい寛容な文化があるので、そのなかで締め切り厳守を貫けば、結構目立つことができるかもしれません(笑)。というのは冗談半分ですが、例えばハリウッドから出た“Me Too”運動がすぐに世界中に拡散したように、日本もそれ以外の国も、同じ空気を共有している側面はあるわけです。そのなかで出てくる小説は、なるだけリアルタイムで翻訳出版するほうが、よりよく理解されると思うんですね。もちろん、時代を超える傑作だとそんな心配はいらないですが。そうした状況もありますから、なるだけ仕事は早いほうがいいと思いつつ、僕自身はだんだん締め切りが守れなくなってきているので、この課題は次世代の翻訳者の方々に託そうと思います(笑)。
取材協力
藤井光さん
1980年、大阪府生まれ。北海道大学大学院文学研究科博士課程修了、同志社大学文学部英文学科准教授。
訳書に『死体展覧会』、『すべての見えない光』、『煙の樹』、『奪い尽くされ、焼き尽くされ』、『紙の民』、『タイガーズ・ワイフ』、『夜、僕らは輪になって歩く』、など多数。著書に『ターミナルから荒れ地へ 「アメリカ」なき時代のアメリカ文学』、編著に『文芸翻訳入門 言葉を紡ぎ直す人たち、世界を紡ぎ直す言葉たち』など。