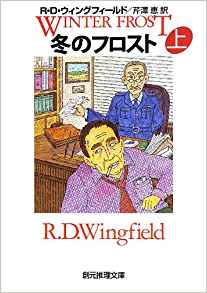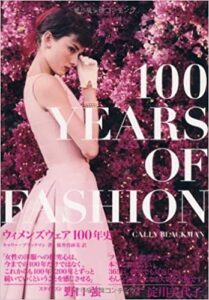FEATURES
『冬のフロスト』
全6作品すべてがミステリランキング1位に輝いた、R・D・ウィングフィールドによる超人気警察小説です。
翻訳を手がけた芹澤恵さんに、このシリーズの魅力などをうかがいました。
- 【作品紹介】
- 冬のデントン署はまたしても忙しい。幼い少女の行方不明や、娼婦の連続惨殺などで、署員はおおわらわだ。そんななかフロスト警部は、とことんダメな部下モーガン警部とマレット署長に足を引っぱりまくられ、さらにはモード部長刑事の戦線離脱という苦境にさらされながらも、いつもの軽口を武器に寝る間を惜しんで事件解決に奔走する。フロスト警部シリーズ第5弾。
シリーズの魅力である
「てんこ盛りの愉しさ」が味わえます
これまでのシリーズと同様、モジュラー型の警察小説。酔っ払いのフーリガンがバス一台分、警察署に押しかけて大騒ぎになり、枕カヴァーを使う侵入窃盗事件が頻発し、娼婦ばかりが狙われる連続虐殺事件に行方不明の少女が他殺体で発見され、さらに裏庭から白骨体が掘り出されて……というふうにいくつもの事件が同時多発的に発生して、互いに関係があるのかないのか、よくわからないまま物語が進んでいきます。そのスタイルもこれまでの作品と変わっていません。読みどころは……ひと言で言うのが難しいですが、やはり本作もまた「てんこ盛りの愉しさ」でしょうか。筋立てにしてもキャラクターにしてもなんにしても、単体で見るとわりと小粒ですが、それが「これでもかっ!」と盛りに盛られている、その過剰感のようなものがこの作品の、もしくはこのシリーズの魅力なのではないかしら、と思っています。
このシリーズがここまで日本の読者に受け入れられているのは、次の作品が出るまでに長く間が空いているから……というのは半分冗談ですが、半分はそれも理由かもしれません。毎回、モジュラー型というスタイルが変わるわけではなく、扱われる事件もごく一般的なものだし、シリーズものですから登場人物も同じ顔ぶれ、しかもどの作品もボリュームたっぷり。訳者は翻訳作業で原作と濃密につきあうため、どうしても作品に対して眼が厳しくなりすぎます。それで、毎回変わらないことが飽きにつながりはしないか、と危惧するのですが、担当の編集者氏曰く「いいんです、毎度お馴染みの水戸黄門的なとこが好まれてるんですから」。これをうんと都合良く解釈するなら「定番として安心して愉しめる」ということかもしれません。それがひとつ、受け入れていただけている理由なのかも、と思います。Twitterで「行きつけの定食屋の魅力」と感想を書いてくださった方がいた、と編集者氏から聞いて、シリーズものの訳者としてしみじみ嬉しくなりました。
あとは強いて挙げるなら、登場人物がそれぞれにひと癖もふた癖もあって、個性的でありながらその人間くさい部分がいかにも身近にいそうなところ、でしょうか。個人的には、主人公のフロストが露骨すぎるぐらい正直に本音を口にするところに共感を覚えてくださる方もいるのではないか、と思っています。一見すると、傍若無人とも思える言動は、ときに照れ隠しだったりもして、そのあたりも日本の読者には受け入れていただきやすいキャラクターなのかもしれません。
本シリーズは「変わらない」と申し上げましたが、実は骨格は変わらないものの、作数を重ねるうちに肉付けの部分に少しずつ変化が生じてきているように思います。最初のころは人物造形に凝るタイプの作家と思っていたのですが、3作目の『夜のフロスト』あたりから筋をいかに複雑に張りめぐらせるか、に力点がシフトしてきているような印象を受けるようになりました。各作品の持ち味をそこなわないよう、でもシリーズとしての統一感も味わっていただけるよう、匙加減を考えねばならず、それはシリーズものならではの大変さかもしれない、と感じます。
『冬のフロスト』でも、メインとなる大きな事件の動機の記述が薄くて、訳者としては物足りないと感じましたが、かといって、書かれていないことを訳すわけにはいかず……本作はその部分の翻訳にいちばん苦労しました。
もうひとつ本作の特徴としては、シリーズ中初めて、フロストよりも“駄目な部下”のモーガン刑事が登場しますが、こちらは人物の造形が肉厚で、そのまま原文に寄り添って訳していくだけでよく、愉しみながら翻訳を進めることができました。
また、シリーズのアイデンティティーでもある下ネタとジョークについて、知りあいのイギリス人でよく本を読む人に訊いてみたところ、フロストのジョークはそれほど冴えているわけではないそうです。本書の解説で養老孟司先生もお書きになっているように「同僚も笑わない冗談を言う」というのがフロストの人物造形でもあるようなので、敢えて冴えない駄洒落や下ネタを連発させているのかもしれません。イギリスでは政治家とあわせて皇室のメンバーも、テレビでも新聞でもわりとよくジョークのネタにされているように思います。「皇太后ばあちゃん陛下」という表現でさえもまた、さほどオリジナリティのあるジョークではない、ということかもしれません。フロストの場合、ジョークそのものよりも、ジョークを発する設定というか……「こういうタイミングでそういうことを言っちゃう?」とか「そういう相手にそんなことまで言う?」の部分が読みどころのような気がします。
最後の作品は『フロスト始末』 ですが、『冬のフロスト』からしばらく間が空いて書かれた作品です。基本的な骨格はシリーズの既刊作品と大きく変わりはありませんが、フロスト警部が心なしか気弱になっている、というか内省的な面を見せているようで、それはたぶんタイトルに暗示されているように、警部に残された日々が……これ以上はネタばれになってしまうので、このあたりで。気弱になっても、内省的になっても、それでもフロスト警部はまだまだ枯れず、かなり傍若無人に暴走します。その迷走ぶりも、どうぞお楽しみください。
取材協力
芹澤恵さん
文芸翻訳家。『フランケンシュタイン』(新潮文庫)、『ハオスフラウ』『密林の夢』(早川書房)、 『フロスト警部』シリーズ、『地球の中心までトンネルを掘る』(東京創元社)、『1ドルの価値/賢者の贈り物 他21編』(光文社)、『夜風にゆれる想い』(二見書房)、『クラッシャーズ 墜落事故調査班』(文藝春秋)、『世界を変えた100人の女の子の物語』(河出書房)など訳書多数。