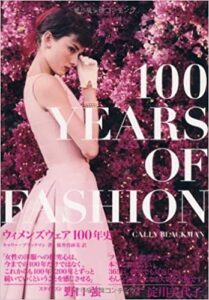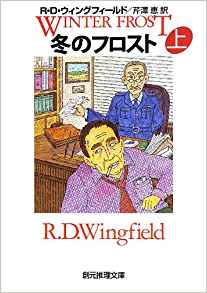FEATURES
『キャロル』
2016年に映画化された本作は、1950年代に発表されたサスペンス作家による女性同士の恋愛小説という、異色ずくめの作品です。
ジャンルの今後なども含めて、訳者の柿沼さんにうかがいました。
- 【ストーリー】
- テレーズは19歳の女性。舞台美術家を目指すもなかなかものにならず、恋人のリチャードとも煮え切らない関係が続いている。そんなある日、テレーズはアルバイト先のデパートのおもちゃ売り場で、ひとりの美しい女性と出会う。テレーズが思い切ってクリスマスカードを出すと、驚いたことに女性から返事があった。女性の名はキャロル。この出会いをきっかけに、ふたりは戸惑いながらもお互いに惹かれていく。
「不安の詩人」ハイスミス
最初で最後の恋愛小説
―― まずは、作品について簡単な解説をお願いします。
舞台となるのは1950年代初めのNY。経済的理由からクリスマス・シーズンまっさかりのデパートで働く19歳の舞台美術家の卵テレーズは、娘のためのクリスマスプレゼントを買いに来たミステリアスな金髪女性に心を奪われます。女性の名前はキャロル。娘の親権をめぐって離婚訴訟中の美しい人妻でした。婚約者がいながらも自分のアイデンティティにとまどっているテレーズのキャロルに対する憧れは、やがて恋に変わり、キャロルもまた年若いテレーズの一途さにとまどいながらも、徐々に彼女を受け入れていきます。やがてふたりはキャロルの夫の嫌がらせや、テレーズに結婚を迫る婚約者から逃れるようにして、NYを離れ西に向かって自動車旅行に出ます。その旅がふたりの運命を、ひいてはふたりの関係をも変えていくことになるとは知らず……と、こんな感じでしょうか。
―― 作者のパトリシア・ハイスミスについても教えていただけるでしょうか。
パトリシア・ハイスミスはアメリカ出身ですが、本国よりもむしろヨーロッパで人気を博した小説家です。カレッジ時代から短編を投稿し、最初の長編『見知らぬ乗客』がサスペンス映画のヒッチコック監督によって映画化され、さらに『太陽がいっぱい』がルネ・クレマン監督で映画化されることでサスペンス小説作家としての名声を確立しました。彼女がもっとも得意とするのは、孤独で不安定な人間が、わずかな齟齬や思い込みがもとで、まわりの人間たちを巻き込みながら破滅していくという心理サスペンスであり、カタルシスとは無縁な、読者を突き放すような結末はどちらかといえば今はやりの「イヤミス」に近い気がします。作中人物のみならず、読者までも不安におとしいれずにはおかない繊細な心理描写には定評があり、グレアム・グリーンはいみじくも彼女を「不安の詩人」と呼んでいます。
―― そんな作者の作品としては、かなり異色の位置づけになりそうですね。
はい。「不安の詩人」「イヤミスの祖」ハイスミス最初で最後の恋愛小説(笑)というところでしょうか。
―― 現在では社会的に性の多様性が認められつつありますが、女性同士の恋愛を作品の中心に据えるのは、当時としては相当に大胆な試みだったように思います。
この作品が発表された1951年は、マッカーシズムの赤狩り旋風が吹き荒れている真っ最中でした。東西冷戦下で、弱みを持つ同性愛者は共産主義者に狙われてスパイになりやすいという理屈のもとに、男女双方の同性愛者は徹底的な弾圧を受けることになります。ひとたび同性愛者だということがばれれば、即刻追放されるか、精神病院で治療を受けて「正常」になることしか許されないような時代でした。小説や映画などでもアンハッピーエンディングでなければポルノ扱いになって、一般読者の目に触れることはできなかったのです。そうした時代背景を考えると、ハイスミスという名前を使えず別名義で発表されたとはいえ、『キャロル』のエンディングはかなり大胆な結末だったといえるでしょう。それゆえ『キャロル』は現在のLGBT文学においては古典的な位置を占めています。
―― 巻末に付された原書の2010年版序文には、「ようやく読まれるのにふさわしい機が熟した」とあります。LGBTは柿沼さんのご専門のひとつでもありますが、今後は数も増えていきそうですね。
LGBTをテーマにした作品自体は英米で1980年代からメインストリームの一部となりつつありますが、日本では1990年代に一時的に翻訳ゲイ文学ブームが起きたあとは、なかなか紹介されていないのが現状です。とはいえ、近年は序文を寄せたヴァル・マクダーミドをはじめとしてサラ・ウォーターズやアンネ・ホルトといったミステリ系のレズビアン作家が日本でも受けいれられるようになってきたので、これを機に日本でもハイスミスの再評価がなされることを大いに期待したいと思います。
―― 作品そのものについても教えてください。テーマとしては他のハイスミス作品とは一線を画す本作ですが、文章の面では何か特徴はあるのでしょうか。
ハイスミスの文体の特徴は、かなりハードボイルドというか、突き放したところから人間のイヤな部分をねちねちと書き込んでいくところにあり、それはこの『キャロル』においても変らないのですが、時折噴き上げる「乙女」が全開になるのが異色といえば異色かもしれませんね。全体的に1950年代当時の、もしかしたら明日にも核戦争で世界が滅びるのではないかという当時のアメリカ市民が抱いていた「不安」が色濃くにじみ出ていると思います。そうした未来に対する漠然とした「不安」とは対照的に、キャロルに対する愛情はあまりに圧倒的かつ鮮烈で、テレーズは絶望と有頂天のあいだをジェットコースターのように行き来することになります。これはとりもなおさず若き日のハイスミス自身の心境だったのではないかと思います。
―― たしかに、女性らしさが全開だというのは読んでいて感じました。その部分を含めて、翻訳で気をつけた点、あるいは印象に残っている箇所はありますか?
1950年代初頭の作品なので、用語などにあえてややレトロな感覚を心がけた部分もあります。たとえば女性同士の会話などですね。一番訳していて印象的だったのは、テレーズのミセス・ロビチェクという年配の女店員に対する異様なまでの嫌悪感でしょうか。若さゆえの傲慢といいますか、醜さや老いに対する容赦のなさというか(笑)。まさにハイスミス節全開というところです。なのにテレーズは彼女を嫌いながらもずっと気にかけずにはいられない。もし才能がない凡人だったらこうなるかもしれないという、絶望的な未来の自分の姿を彼女に見ているからなんですね。それがキャロルという絶対的な美との壮絶な対比をなしているともいえます。
―― ありがとうございました。最後に、学習中の方へのメッセージをお願いします。
「好きこそものの上手なれ!」このひとことにつきますね。
取材協力
柿沼瑛子さん
出版翻訳家。『キャロル』(河出文庫)、『わが愛しのホームズ』(新書館)、『聖なる槍に導かれ』『闇の王子と求め合って』(ヴィレッジ・ブックス) 、『性の悩み、セックスで解決します』(イースト・プレス)、『未来に羽ばたく三つの愛』『今甦る運命の熱い絆』「ヴァンパイア・クロニクルズ」シリーズ(扶桑社)、『滅亡の暗号』(新潮社)など訳書多数。