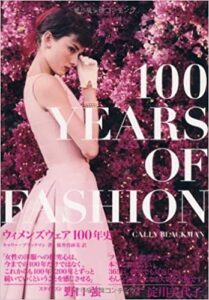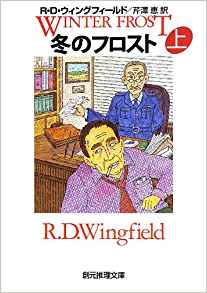FEATURES
『あるときの物語』
登場人物の生き生きとした語り口や、ところどころに挿入される存在と時間をめぐる思想など、本書の魅力について田中さんにうかがいました。
- 【作品紹介】
- カナダの小島に住むルースは、ある日、浜にハローキティの弁当箱が打ちあげられているのを見つける。なかに入っていたのは本物の本のように装幀された日記帳。ナオと語る書き手は、学校でのイジメや104歳の曾祖母、そして自殺を考えていることなどについて綴っていた。ルースは日記を読み進めるうち、ナオの行く末を案じるとともに、作家としての自分とも向き合うようになっていく。
圧倒的な存在感を持つヴォイスに耳をすまし、感じたままに訳す
カナダのブリティッシュコロンビア州の小島に住む日系人作家のルースはある日、浜辺を散歩中にハローキティの弁当箱が打ち上げられているのを見つけます。夫のオリバーが「東日本大震災の漂着物かもしれない」と示唆したその弁当箱の中には、東京の中学生ナオが書いた日記、古い手紙、年代物の腕時計がはいっていました。日記の中でナオは、仙台に住む曾祖母である104歳の尼僧、自殺願望のある父親、カミカゼ特攻隊員だった大伯父、日本の中学校で遭った壮絶なイジメなどについて書いていて、自分自身も自殺するつもりだとほのめかします。日記を読み進むうちにルースはナオを助けたいという差し迫った思いに駆られていくのですが、そんなルースにオリバーは、日記は10年以上もまえに書かれたものなのだから、ナオが自殺するつもりならもうとっくにしているはずだと指摘します。それでもルースはナオに対する現在進行形の心配をぬぐい去ることができません。ナオは自殺するのだろうか。それとも、震災の犠牲になってしまうのだろうか……。そうしたことを軸に物語が進んでいきます。
原文を初めて読んだときにまず印象に残ったのは、ナオのヴォイスの圧倒的な存在感でした。著者は、ナオのヴォイスは初めからそこに存在していて、自分はただそれに耳をすまして聞き取るだけでよかったと語っていますが、そんな揺るぎない存在感のおかげで、ナオの日記を訳す際も、原文から感じたままに訳すことができました。なにしろほんとうに声が聞こえてきそうだったからです。ほかの登場人物についても、ひとりひとりくっきりと造形されていましたので、訳で個性を出したというよりも、感じたとおりに訳したという感じで、それはとても楽しい作業でした。まさしく原文の力だと思います。
ナオは日記の中で「わたしの未来のどこかに存在する“あなた”に宛ててこれを書いている」と言っているのですが、その“あなた”というのはルースでもあり、本書を手にとって読んでいる私たち読者でもあるという気がします。本書の最大のテーマは書き手と読み手のあいだに生まれる関係性であり、著者はそれを「魔法」と呼んでいます。それがどんな「魔法」なのか、本書ではそのひとつの形が、わくわくするストーリー展開とともに提示されています。
本書の根底には、『正法眼蔵』の概念に基づいた時間と存在についての考察というテーマがあるのですが、一見倦厭してしまいがちなそうした難解なテーマを、ナオという少女があれこれ考えながら、半分茶化しながら、いかにもティーンエージャーらしい文体で書いているので、そうしたテーマの持つ哲学臭みたいなものがうまく中和されています。いくつもの謎解きや仕掛けも用意されているページターナーでありながら、付箋をいっぱい貼ってしまいたくなるような深い言葉がちりばめられている点も、本書の大きな魅力だと思います。
禅の思想については、まずはネットなどでおおまかな知識を得たあとで、最終的には図書館で『正法眼蔵』の現代語訳を借りてきて読みました。また、量子力学も絡んでくるのですが、そちらについてもほとんど知識がなかったので、解説書などを何冊か読みました。調べ物は大変でしたが、読めば読むほど興味がわいてきて、いつのまにか関係のないところまで読みふけっているということがよくありました。
著者のルース・オゼキはアメリカのコネチカット州でアメリカ人の父と日本人の母のもとに生まれました。スミス・カレッジにて英文学とアジア研究で学位を取得したあと、文部省の留学生として奈良女子大学院で日本古典文学を学びました。1985年に帰国してドキュメンタリー映画などの制作にたずさわったあと、1998年に長編『イヤー・オブ・ミート』を発表し、大型新人として注目を集めました。20013年には第2作『All Over Creation』を発表しています。2003年に刊行された本書は、ブッカー賞最終候補となり、全米批評家協会賞にもノミネートされました。オゼキ氏はまた、2010年に曹洞宗の僧侶となっています。
著者によれば、本書はもともと〈ルース〉ではない別の人物を日記の読み手として書かれたそうなのですが、完成した原稿を編集者に送ろうとした矢先に東日本大震災が起こったとのことです。そこで、未曾有の大惨事のあとの現実世界により直接的に関わるためには、フィクションという器を壊して自らが読み手となる以外にないと感じ、自身のセミフィクショナルなバージョンである〈ルース〉を読み手として最初から書き直したそうです。
ナオの日記に登場する104歳の尼僧のジコウが住むお寺は、仙台の山奥にあります。私は仙台在住ですので、それがどこなのか、具体的な記述はないのですが、本書を訳しながらずっと、あの辺なのではないかと想像していました。地元ということで、やはり風景や雰囲気などはイメージしやすかったと思います。
フェロー・アカデミーでは通信講座を受講後、田口俊樹先生のゼミに仙台から月1回通学しました。田口先生の言葉で今もずっと忘れずにいるのは、「訳文はリズムがなにより大切」という言葉です。生徒の訳文を読む際、先生は「ここからちょっとリズムが崩れている」とものすごく鋭く指摘されるのですが、その「ちょっと」がなかなかわからず、私も先生と同じような敏感なセンサーを身につけたいとずっと思っていましたし、それは今も変わりません。プロの翻訳家から直接教わって得られることは非常に大きいと思いますので、地方在住の方でも、チャンスがあったらぜひそういう機会を持たれることをお勧めします。
取材協力
田中文さん
川副智子先生のマスターコースで学んだあと、「翻訳パドック」を経て田口俊樹先生に師事。訳書は『フリント船長がまだいい人だったころ』『病の皇帝「がん」に挑む』(早川書房)。